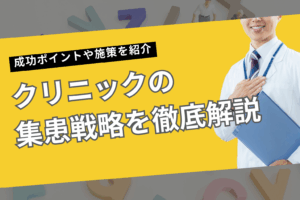美容医療業界において、デジタルマーケティングの重要性はますます高まっています。
特に医療記事の制作は、患者様との信頼関係構築と安定した集患を実現する重要な施策です。
本記事では、効果的な医療記事制作の方法から外注先選定のポイントまで、実践的な情報をお届けします。
クリニックの「Webマーケティング」に
取り組もうと考えている医院・クリニックさまへ

Clinic Clickは、医療・美容クリニック専門のWebマーケティングの総合支援サービスです。
医療広告ガイドラインを考慮したコンテンツマーケティング/広告運用だけではなく、Webマーケティングの戦略立案、SNSマーケティング、Webサイト改善、毎月のレポーティングなど、豊富な経験と実績を持ったメンバーたちがPDCAを実行し、丁寧にサポートします。
医療記事制作の効果
自院のWebサイトで医療記事を制作することで、患者様への認知拡大や信頼性向上が図れ、結果として集患に繋がります。
短期的な集患効果を狙う広告と異なり、医療記事は一度制作すれば貴重な資産となり、継続的に集患効果を発揮するだけでなく、費用を抑えつつ長期的に安定した集患を実現できるのが医療記事制作の大きなメリットです。
特に競争が激化している美容医療市場において、専門性の高い情報発信は他院との差別化にも繋がります。
医療記事制作で押さえるべき基本要素
美容クリニックの医療記事制作では、以下の重要な要素を理解し、適切に対応することが成功の鍵となります。
YMYL
健康やお金に関わる情報は「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれ、正確性と信頼性が重視されています。
特に美容医療は患者様の健康と外見に大きな影響を与える可能性があるため、Googleも他ジャンル以上に厳しく評価しています。
美容クリニックの医療記事もこのYMYL領域に該当するため、YMYL領域の記事はアルゴリズムの影響を受けやすく、サイト全体で信頼性を高める工夫が必要です。
E-E-A-T
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、GoogleがWebサイトを評価する指標のひとつで、YMYL領域では特にE-E-A-Tが重視されます。
美容クリニックにおいては、医師の実績や症例数、学会発表歴などが権威性の向上に繋がります。
検索順位だけでなく、Googleの検索結果に表示されるAIの概要(AI Overview)での引用にも影響するため、継続的な信頼性向上の取り組みが重要です。
医療広告ガイドライン
医療記事は、医療広告ガイドラインという法的な規制の対象となります。
美容医療では特に、施術の効果や安全性に関する表現に注意が必要です。不適切な表現を用いた場合、行政指導の対象となる恐れがあります。
一度ペナルティを受けると流入の回復に多大な時間と労力が必要となるため、日頃からガイドラインを遵守した表現が求められます。
医療広告ガイドラインについては、最新の情報を以下の記事でまとめておりますので、チェックしてみてください。
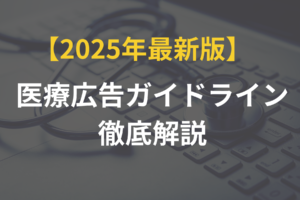
集患に繋がる医療記事の制作ステップ

効果的な医療記事制作には、体系的なアプローチが重要です。
以下のステップに沿って進めることで、集患効果の高い記事を制作できます。
ペルソナを設計する
記事で伝えるべき相手(ペルソナ)を明確にします。
美容クリニックの場合、年齢・性別・悩み・美容に対する関心度・予算感などを具体化することで、共感されやすく、情報提供に一貫性のある記事が作成できます。
例えば、「30代前半の働く女性で、シミやそばかすに悩んでおり、初回の美容治療を検討している」といった具体的な患者像を設定します。
キーワード選定を実施する
ペルソナや自院が事業として伸ばしていきたい治療からキーワードを選定します。
また、検索ボリュームや競合状況を確認しながら、自院が上位表示を狙えるキーワードを選定することが重要となります。
患者様からよくいただく質問やSNSでの声も参考にしながら、リアルなニーズを把握することで、より効果的なキーワード選定が可能になるでしょう。
記事構成を考案する
上位表示されている他サイトの構成を参考にしつつ、検索意図を網羅できるような構成を作成します。
さらに自院の強みや治療方針を活かすことで、他院との差別化にも繋がります。
美容クリニックの場合、施術の流れ、ダウンタイム、料金体系、アフターケアなど、患者様が知りたい情報を体系的に整理することが重要です。
記事を執筆する
構成案に沿って記事を執筆します。
論文などの一次情報をもとに、正確で根拠のある内容を盛り込みます。美容医療では、症例写真なども活用すると、視覚的な訴求力が高まります。
専門用語を使用する際は、患者様にも理解しやすい表現での補足説明を必ず加えることで、読者の理解促進と離脱防止に繋がります。
内容をチェックする(編集・校正)
誤字脱字や論理の矛盾、誤った情報がないかなどをチェックし、読みやすく整えます。
美容クリニックの場合、特に医療広告ガイドライン違反の表現がないかを入念に確認する必要があります。
効果に関する断定的な表現や、他院との比較表現などは特に注意が必要です。
医師による監修を行い、修正・確定する
医師や有資格者に最終確認を依頼します。
医学的な誤りの有無や、自院の治療方針との整合性を確認してもらい、必要な修正を加えたうえで内容を確定します。
美容医療では、施術の適応や禁忌事項、リスクに関する情報の正確性が特に重要になります。
公開作業を行う
CMSへの入稿作業では、ハイライトや表の活用など視認性を高める工夫を行います。
SEOを意識して、タイトルタグ・メタディスクリプション・画像のalt属性なども適切に設定します。
美容クリニックの場合、ビフォーアフター写真や施術風景の画像も効果的に活用し、視覚的な訴求力を高めることが重要です。
効果検証し、必要に応じてリライトする
記事公開後は、検索順位や流入数、さらには問い合わせ数や予約数への影響を確認し、必要に応じて内容を見直します。
公開直後は順位が安定しないため、2〜3カ月経過後にリライトの判断をします。
美容医療では季節性のある施術もあるため、時期に応じた情報更新も効果的です。
医療記事制作における注意点【医療広告ガイドライン】
美容クリニックの医療記事制作では、医療広告ガイドラインの遵守が不可欠です。以下の点に特に注意が必要です。
比較優良広告
自院が他院よりも優れていることを広告するのは認められていません。
「地域No.1」「最高品質」「他院では真似できない技術」といった表現は避ける必要があります。
競合との差別化を図るため、客観的事実に基づかない優位性の主張は禁止されています。
誇大広告
事実を誇張した表現や、患者様に誤解を与えるような広告は禁止されています。
「確実に美しくなる」「必ず効果が出る」「リスクゼロ」といった断定的で誇張した表現は使用できません。
美容医療では個人差があることを必ず明記し、現実的で適切な期待値を設定することが重要です。
価格の強調
費用を記載する場合は、過度に強調せず、適切に表示する必要があります。
「激安」「破格」「業界最安値」といった過度な価格訴求や、キャンペーンを過度にアピールするなど、医療の品位を損ねる広告は避けなければなりません。
料金表示の際は、税込み価格での明記や、追加費用が発生する可能性がある場合の注記も重要です。
体験談や口コミの掲載
体験談や口コミは、患者様の個々の状態によって変わる可能性があるため、広告として掲載するのは認められていません。
「患者様の声」として具体的な効果や満足度を記載することは禁止されています。
ただし、サービス全般に関する感想(接客態度やクリニックの雰囲気など)は掲載可能な場合があります。
症例写真の掲載
患者様の個々の状態によって結果が異なるため、治療のビフォーアフター写真は原則として掲載できません。ただし、限定解除要件を満たせば掲載可能です。
美容クリニックにとって症例写真は重要な訴求材料ですが、適切な手続きと注意事項の明記が必要です。

医療記事制作における注意点【その他】

医療広告ガイドライン以外にも、品質の高い医療記事制作のために注意すべき点があります。
信頼性の高い一次情報を使用する
医療記事の正確性を担保するためには、論文などの信頼できる一次情報を活用する必要があります。
美容医療分野では、海外の最新研究や学会発表なども参考にしながら、エビデンスに基づいた情報提供を行ないます。
他サイトの内容を鵜呑みにするのは避け、必ず原典にあたって情報の正確性を確認することが重要です。
専門用語の補足説明を行う
専門用語を多用すると、読者が理解できずに離脱を招く恐れがあります。
美容医療では、施術名や機器名、医学用語が多く登場するため、医学知識のない方でも理解できるよう、簡単な言葉での補足説明を必ず加えます。
図解やイラストを活用することで、より分かりやすい説明が可能になるでしょう。
断定表現を避ける
治療の効果には個人差があるため、「シミが完全に消える」「必ず若返る」などの断定的な表現は避け、「シミの改善効果が期待できる」「若々しい印象を与える効果があるとされている」といった表現で中立性を保つことが大切です。
美容医療では特に効果への期待が高いため、現実的で適切な表現を心掛けることが重要です。
モバイルフレンドリーを意識する
患者様の多くはスマートフォンで検索するため、スマホからでも見やすいサイト設計が大切です。
Googleもモバイルファーストインデックスという仕組みを導入しており、モバイル版のサイトが優先的にクロール・インデックスされます。
美容クリニックの場合、症例写真や施術の様子を見やすく表示することも重要な要素です。
医療記事制作を外注する際のポイント
美容クリニックが医療記事制作を外注する際は、以下のポイントを確認することで、質の高いパートナーを選択できます。
論文をもとにした制作ができるか確認する
美容医療分野では信頼性が欠かせません。
執筆者や制作会社に論文をもとに記事を制作できる能力があるかは必ず確認が必要です。
特に、美容医療の最新トレンドや技術動向にも精通していることが望ましいです。
医療広告ガイドラインに精通しているか確認する
医療記事制作をするうえで、医療広告ガイドラインの観点はスルーできません。
特に美容クリニックの場合、規制が厳しいため、すでに美容クリニックのWebマーケティングを支援した実績がある会社を選ぶと安心です。
過去の制作実績や、ガイドライン違反を防ぐためのチェック体制について確認することが重要です。
Webマーケティングを一貫して支援できる会社を選ぶ
記事制作だけでなく、SEO・SNS・LINE・リスティング広告など、Webマーケティング全体を支援できる会社であれば、施策の一貫性が取れ、集患効果も高まります。
美容クリニックの場合、複数のチャネルを組み合わせた統合的なマーケティング戦略が効果的となるでしょう。
AI Overviewなど最新の情報にも対応しているか確認する
Googleの検索ではAI Overviewの登場により検索結果の表示画面やクリック数・CTRに変化が生じています。
支援会社が最新の情報をキャッチアップしながら記事制作をしてくれるかも、確認が必要です。
美容医療分野でのAI Overview対応実績や、対策方法についても相談できる会社を選ぶことが重要です。
自院のこだわりや強みを整理しておく
差別化の観点から、自院独自の取り組みや価値観を事前に整理し、外注先に共有しておくことで、記事のオリジナリティと訴求力が高まります。
使用している機器の特徴、医師の専門分野、クリニックの理念や治療方針など、他院との違いを明確にしておきます。
院内で記事確認のリソースを空けておく
最終的な内容確認はクリニック側で行なう必要があります。
特に美容医療では医師や専門知識を持ったスタッフによるチェックが不可欠です。リソースが確保できていないと公開が遅れ、施策が進まない原因にもなるため注意が必要です。
定期的な確認スケジュールを設定し、継続的に記事制作を進められる体制を整えることが重要です。
症例写真をストックしておく
限定解除要件を満たせば、症例写真の掲載が可能です。
日頃から症例を記録・整理しておくことで、ビジュアル訴求力のある記事制作が実現しやすくなります。
症例写真はGoogleにも独自性として評価されたり、AI Overviewや強調スニペットなどにも引用されたりなど、流入アップに貢献できます。
患者様の同意書取得や、撮影条件の統一なども重要なポイントです。
医療記事制作で集患を成功させた事例

当社が支援しているクリニック様では、ほくろ治療に関する医療記事制作により、大幅な集患増加を実現しました。
施術の種類や適応、料金体系、ダウンタイムなど、患者様が知りたい情報を網羅的に整理し、症例写真も適切に活用した結果、検索上位表示を獲得。
Webサイトの流入数が約2.5倍に増加し、集患のベースアップを実現されています。
成功事例についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、興味がある方はぜひ参考にしてください。
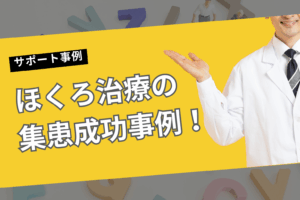
医療記事制作で信頼を獲得し、安定した集患を目指そう!
美容クリニックにおける医療記事制作は、短期的な集患だけでなく、長期的な信頼関係構築と安定した経営基盤の確立に繋がる重要な施策です。
医療広告ガイドラインの遵守はもちろん、患者様の立場に立った有益な情報提供を心掛けることで、競合他院との差別化を図ることができます。
自院での制作が困難な場合は、美容医療分野に精通した専門会社への外注も有効な選択肢です。AI Overviewなどの最新動向にも対応しながら、継続的な情報発信を通じて、患者様に選ばれるクリニックを目指しましょう。
当社ParaWorksでは、これまでに複数のクリニックさまをご支援し、多数のキーワードで検索流入の実績を上げてきました。
Webサイトのアクセスや集患対策にお悩みのクリニックさまは、ぜひParaWorksのClinic Clickへご相談ください。
クリニックの「Webマーケティング」に
取り組もうと考えている医院・クリニックさまへ

Clinic Clickは、医療・美容クリニック専門のWebマーケティングの総合支援サービスです。
医療広告ガイドラインを考慮したコンテンツマーケティング/広告運用だけではなく、Webマーケティングの戦略立案、SNSマーケティング、Webサイト改善、毎月のレポーティングなど、豊富な経験と実績を持ったメンバーたちがPDCAを実行し、丁寧にサポートします。